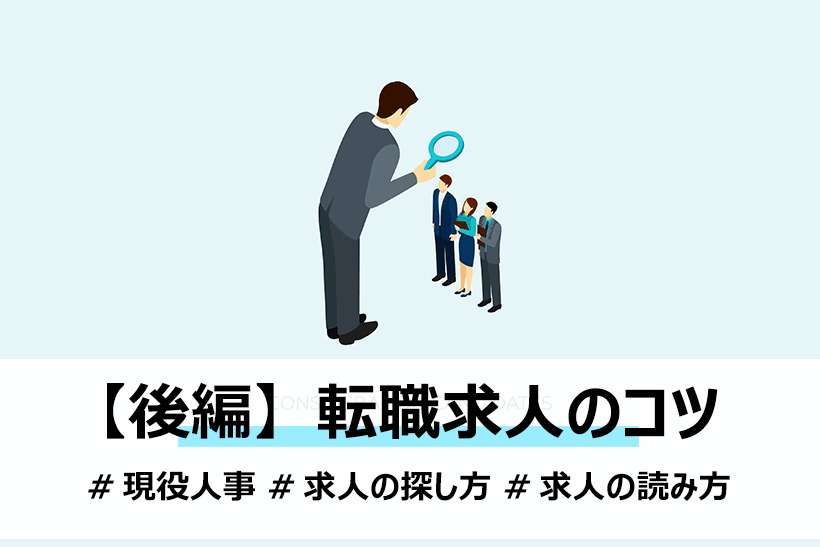転職を成功させるためには、複数の情報源を使って積極的に情報を集めることが成功のカギを握ります。しかし、求人情報に掲載されている情報があいまいで、いまいち内容をつかみきれない…という経験はありませんか?
そこで今回は、前回に引き続き新卒をグループ全体で年間1,000人規模で採用をしている超大手人材会社の現役人事担当者に、あいまいな求人情報をどう読み取ればいいのかを教えてもらいました。
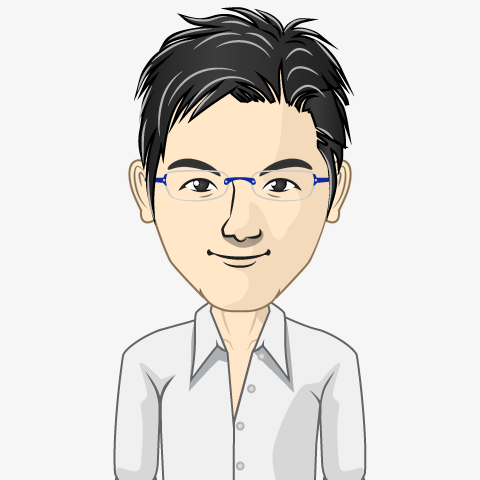
[sc_Linkcard url="https://saiyopro.com/career/jobchangepreparation/3918/" title="前編はこちら" excerpt="【現役人事が教える】転職の求人情報の探し方と読み取り方〜前編〜"]
1.企業は求人情報に書けない情報がある
転職用の求人情報は、仕事内容や募集条件がハッキリと記載されておらず、あいまいな表現になっていて分かりづらい印象があります。
―― 転職者用の募集要項はあいまいな点が多いように感じますが、どうしてなのでしょうか?
山田さん まず、そもそも求人票のフォーマットによっては、書ける文字数に制限があって書き切れないことがあります。そうなると最低限絞った情報しか載せられなくなってしまいます。
そういった事情以外にも、社外に開示できない情報が多いことも、提示する内容があいまいなになってしまう理由として挙げられます。本当に求めている人材と出会うためにはどのようなプロジェクトが進んでいるのか書きたいのが本音ですが、そうもいかないのは人事担当としてジレンマを感じるところです。
―― 募集側も苦労しているということなのですね。
山田さん そうなんです。社内の部署によって、提供してくれる情報量に差がある場合もあります。求人票に書ききれないくらい求める人物像を挙げてくれる部署もあれば、「とりあえずスキルさえあれば」としか言ってくれないところもある。
スキルといっても具体的にわからないので、「営業経験3年以上」とか書くことがあるのですが、経験2年でもスキルさえ満たしていればいいということは普通に考えられるのです。ですので、求人票の条件を満たしていなくても、自分は十分通用すると思うのであれば、積極的に応募してみていいと思います。
2.転職者の年収はグレード分けされている
転職するときには一定の年収制限をかけて仕事を探している人も多いですが、求人票には「350万〜800万円」など幅が広い条件しか掲載されていないことがあります。そうなると、自分がどの程度の給料になるのかわかりにくくなってしまいます。
―― なぜ年収のレンジが幅広く提示されるのですか?
山田さん 例えば、前職では年収がグレードによって5段階に分かれていましたので、求人票には、一番低いグレードの年収と、高い年収の両方を、「おおよそ400万〜1,200万円」といったように載せることにしていました。
ただし職種によっては若手しか募集しないときもあるので、そのような場合はもう少し低いグレードの年収で「おおよそ400万〜700万円」とするときもあります。
3.知りたい情報は面接で積極的に聞いていい
自分が知りたい情報が、求人票にハッキリと記載されていないときには、面接で聞いていいのか気になるところです。
―― 気になる情報が開示されていないときには、面接で聞いてもいいものでしょうか。公開されていないことを聞くのはマナー違反とされますか?
山田さん まず、採用対応をする私たち人事側も、求人票にはっきりした情報を開示していない自覚はあります。ですので、真剣に入社を考えていただくためにも、気になることは面接で聞いていただいて構いません。むしろ聞いていただけたらその人が転職にあたって何を重視しているのかわかるので参考になりますね。
―― 重視しているポイントがわかれば、入社後のミスマッチも少なくなりそうですね。
山田さん おっしゃる通りです。人事としては、入社後に「こんなはずじゃなかった」とすぐに辞められるのが一番困ります。そのような事態を避けるためにも、気になること、知りたいことは面接で聞いてもらったほうが結果的にお互いのためになると思います。
たとえば「求人票には○○と書かれていましたが、具体的にどのようなミッションを抱えていて、どのようなスキルが必要と考えていますか?」と、自分のスキルと照らし合わせて入社後のミスマッチが起こらないように考えてくれる人は好印象です。
もちろん入社するまでお伝えできないことは多々ありますが、こちらも条件にあう人材を採用したいと考えていますので、出せる範囲の情報はできる限りお伝えするようにしています。
積極的に質問する姿勢はプラスにしかなりませんので、回答が得られる、得られないにかかわらず、疑問点はしっかり確認することをおすすめします。
4.まとめ
内容があいまいでつかみづらい転職での求人票をどう読み取るといいのかを、山田さんに教えていただきました。
フォーマットの物理的な問題や、情報開示の問題から、内容があいまいになりがちなのが転職での求人票です。その分、記載されている情報が全てではないととらえ、条件に達していなくても応募してみる積極性が吉とでる可能性もあります。
面接まで至った場合には、知っておきたいことをきちんと確認することが、最終的にはミスマッチを防ぐことになるのです。
[sc_Linkcard url="https://saiyopro.com/career/jobchangepreparation/3918/" title="前編はこちら" excerpt="【現役人事が教える】転職の求人情報の探し方と読み取り方〜前編〜"]